 こちらもおすすめ
こちらもおすすめ
 気になる病院を検索!
気になる病院を検索!
次にレジナビWebで
気になった病院を検索しましょう。
Bookにない情報もあるかも。
- 病院ページをブックマークしよう
- 病院情報を見比べてみよう
病院情報どこみたらいいの?という方は
「病院情報のチェックポイント」へ - 病院ページ、またはMyページから資料請求をしよう
医学生用の資料を作って資料請求を待っている病院もあるので、
Webだけではわからない情報を得られるかも!?
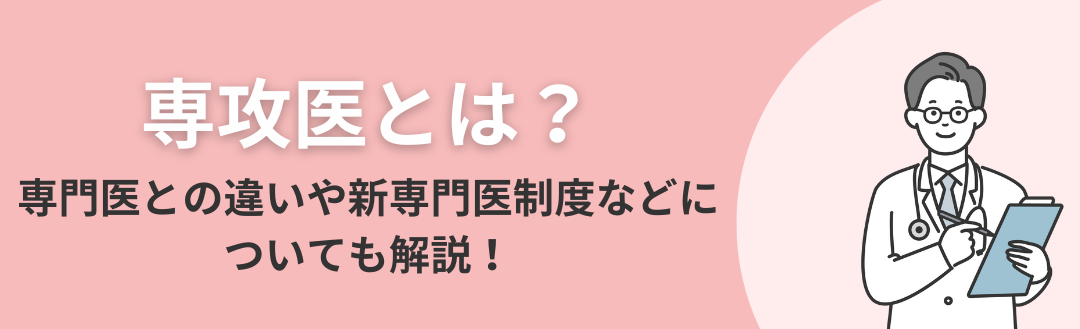
「専攻医」とは、専門領域の診療について研修を受けている医師
専攻医とは、初期研修を終え、専門研修プログラムを受けている医師を指します。
初期研修が2年以上かかるため、専攻医になるのは3年目以降。専門研修を修了することで、プログラムに基づく適切な教育を受け、十分な知識・診療の技能を修得した医師を指す「専門医」試験の受験資格を得られます。専攻医は、従来「後期研修医」と呼ばれていましたが、2018年4月から始まった新専門医制度によって呼び名が変わりました。
医師国家試験合格後の医師のキャリアの流れ(研修医・専攻医・専門医)
ここでは、医師が「専門医」になるまでの、基本的なキャリアの流れを見てみましょう。まず、医学部を卒業し、医師国家試験に合格すると医師として勤務が可能になります。医師としてのスタートは、約2年間の「初期臨床研修」。
この「初期臨床研修」を受ける医師が、「研修医(初期研修医)」です。
基本的な診療知識・スキルを身につけるため、様々な診療科をローテートし研修を受けます。具体的には、内科や救急、外科、小児科、産婦人科、精神科、地域医療などの経験を積みます。その後、大半の医師が「専門研修」に進みます。
自身の専門領域を決め、この「専門研修」を受ける医師が「専攻医」です。
この専門研修は基本的な診療知識・スキルを身につける「初期臨床研修」とは異なり、特定の診療科についての診療知識やスキルなどを学ぶもの。また、専攻医になると診療行為を含むアルバイトが解禁されます。
「専攻医」が研修プログラムに合格すると、「専門医」の資格を取得できます。
研修医から専攻医になるまでにどのような手順を踏めばよいのか、疑問に思う人もいるでしょう。ここでは、「2025年度」の専攻医募集スケジュールを例に挙げ、研修医から専攻医になるまでにどのような手順を踏めばよいのかについて解説します。
2025年度の専攻医募集スケジュール例
1.専攻医登録・応募
2.プログラムの選択
3.一次募集に応募<11月初旬~中旬>
4.面接、試験
5.合格発表<11月下旬>(合格の場合:採用通知)
6.(5で不合格の場合)二次募集に応募<12月初旬~中旬>
1.専攻医登録・応募
日本専門医機構ホームページ、もしくは、専門研修希望領域(学会)のホームページから、専攻医登録サイトにアクセスし、自分の専攻医基本情報を登録します。
このとき、氏名や生年月日、医籍登録番号・登録年、登録時点で希望する専攻診療領域などの登録が必要です。
2.プログラムの選択
専攻医登録サイトに各研修プログラムが掲載されるため、詳細を確認のうえプログラムを選択します。
3.一次募集に応募<11月初旬~中旬>
応募締め切りまでに、希望する施設の見学を行い、一次募集の応募先を決めます。その後、専攻医登録サイトから応募するという流れです。
応募は1領域の1プログラムのみになるので、応募前によく考え自身で決めたうえで応募しましょう。
4.面接、試験
応募の締め切り後、病院のプログラム統括責任者から詳細の案内が届き、プログラムごとに面接や試験が行われます。
5.合格発表 <11月下旬>
プログラムごとの選考基準に基づき、試験の合否が決まり、応募者に通知が届きます。合格の場合は採用通知が届くので、そのあと、プログラム統括責任者の指示に従って、翌年からの研修の準備を行います。
6.(5で不合格の場合)二次募集に応募<12月初旬~中旬>
不合格の場合でも、二次募集に応募が可能です。再度プログラムの選択を行います。また、一次募集に応募しなかった人も二次募集への応募が可能です。
専門医制度とは、新専門医制度の前身といえる制度のことです。ここでは、専門医制度とはどのような制度か、新専門医制度発足の背景について解説します。
専門医制度(旧専門医制度)とは?
専門医制度(旧専門医制度)とは、各診療科・領域におけるスペシャリストを育成し、質の高い医療を提供することを目的に生まれた制度です。旧専門医制度では、学会ごとに独自の認定プログラムが運用されており、そのプログラムを修了することで専門医の資格取得が可能でした。しかし、旧専門医制度にはいくつかの課題が見つかったため、国民に対するより良質な医療の提供と育成される医師のキャリア形成支援を目的とした「新専門医制度」が2018年に設立されました。
新専門医制度設立の背景
新専門医制度の設立の背景には、旧専門医制度の時代にあった以下の2つの課題があります。
・専門医ごとの質の差
・医師の数の偏り(地域ごと、診療科ごと)
各学会がそれぞれ専門医の認定基準を持ち、医師に専門医の資格を付与できる状態であった旧専門医制度は、専門医の資格を取得できる難易度が学会によって異なり、専門医の知識やスキルの質にばらつきが出てしまう原因になるとされていました。患者さんにとって、医師の技量は治療を受ける上で重要なポイントです。どの医師が担当になっても、患者さんが安心して治療を受けられるよう、医師のスキルの質を一定以上にする必要がありました。
加えて、新専門医制度設立には、地域や診療科による医師の人数の偏りという課題も関わっていました。例えば、都市部は医師の人数が多いのに対し、地方では深刻な医師不足により休診を余儀なくされる医療機関が発生。また、業務の忙しさや訴訟リスクなどによって医師の数が診療科ごとに異なるなどの傾向もありました。
時代の変化にあわせ、このような点について改善の余地があるのではないかとの声が次第に大きくなりました。そして、専門医のあり方を見直すため、2014年に第三者機関として日本専門医機構が発足。日本専門医機構は2018年に「新専門医制度」を設立し、研修内容や認定基準を統一しました。その後、新専門医制度に基づき、誰に対しても平等に質の高い医療を提供するための体制づくりが進んでいます。
旧専門医制度に代わって発足された新専門医制度では、どのような研修プログラムが組まれているのでしょうか。ここでは、新専門医制度の専門研修プログラムの内容を紹介します。新専門医制度の専門研修プログラムは、医師の専門性を向上させるため、内容を基本領域とサブスペシャルティの2段階で学ぶ方式になっています。
基本領域について
初期研修を修了した医師は、まず進みたい診療科(基本領域)を選択。そして、専門研修プログラムを持つ医療機関で3~5年間の専門研修を受けます。研修修了後、認定試験に合格すると専門医に。専門医資格は、原則5年ごとに認定更新の審査を受ける必要があります。専門研修ではプログラム制以外に、出産や育児、介護などの専攻医のライフイベントに合わせ学べるカリキュラム制(単位制)も選べます。基本領域の選択は、その後のキャリアを決めるための重要な選択です。
自身がどのような医師になりたいか、よく考えて決めましょう。
基本領域
内科/小児科/皮膚科/精神科/外科/整形外科/産婦人科/眼科/耳鼻咽喉科/泌尿器科/脳神経外科/放射線科/麻酔科/病理/臨床検査/救急科/形成外科/リハビリテーション科/総合診療
サブスペシャルティ領域について
基本領域の研修を終え、認定試験に合格した専門医は、より専門性の高い診療科(サブスペシャルティ領域)の専門医の資格を取得できます。基本領域で専攻した診療科に関連する領域を選択することで、より専門性を深められるのがサブスペシャルティ領域の特徴です。
サブスペシャルティ領域と連動研修について
令和7年12月19日現在の認定領域は以下のようになっています。一部の診療科では、基本領域と同時に研修を受けられる「連動研修」が認められています。
| 研修方式 | 該当するサブスペシャルティ領域 |
|---|---|
| 連動研修を行い得る領域(連動研修方式または通常研修方式) | 消化器内科/循環器内科/呼吸器内科/血液/内分泌代謝・糖尿病内科/脳神経内科/腎臓/膠原病・リウマチ内科/消化器外科/呼吸器外科/心臓血管外科/小児外科/乳腺外科/放射線診断/放射線治療 |
| 連動研修を行わない領域(通常研修方式) | アレルギー/感染症/老年科/腫瘍内科/内分泌外科 |
| 少なくとも1つのサブスぺ領域を修得した後に研修を行い得る領域(補完研修方式) | 肝臓内科/消化器内視鏡/内分泌代謝内科/糖尿病内科/放射線カテーテル治療 |
| 連動研修を行わない領域(通常研修方式) | 集中治療科/脊椎脊髄外科/新生児/小児循環器/小児神経/婦人科腫瘍 |
※引用:日本専門医機構
シーリング制度とは、医師の地域ごと診療科ごとの偏りなどの解消に向けて、医師の採用数を都道府県や診療科に応じて制限する制度です。
具体的には、医師の均衡化を目的とし、すでに必要な医師の数を確保できていると思われる都道府県や診療科にシーリング(限度)を設けます。そして、医師が不足している地域に採用された一部の専攻医を派遣し、研修を受けてもらうというものです。
シーリング制度設置の背景
シーリング制度が設置された理由は、医療業界の大きな問題の一つといわれる「地域や診療科による医師数の偏り」です。この問題を解決するため、新専門医制度のもと2020年より必要な医師数に達している診療科に対して、採用数の上限が設定されました。
シーリング制度と専攻医の関連
シーリング制度は、専攻医に大きく関わる制度といえます。その理由は、2018年に新専門医制度がはじまり専攻医の研修内容が変わったことで、対応できる病院数が減少し、一部の地域・診療科に専攻医が集中したからです。この医師の地域偏在を解消するため、シーリング制度により設けられた連携プログラム枠として、研修プログラムの半分以上をシーリングのない都道府県で実施する対応をとっています。今後も人気の高い地域・診療科は倍率が高くなり、専攻医は研修先選びが難しくなることが予想されます。そのため、専攻医はこのシーリング制度をよく理解する必要があるといえるでしょう。
また、シーリングの枠数は年度ごとに変動するため、日頃から情報収集し、綿密なキャリアプランを立てることが重要です。
以下リンクは、2024年10月時点でのシーリング制度対象の診療科の一覧です。参考にしてください。
シーリング制度対象の診療科
内科/小児科/泌尿器科/脳神経外科/整形外科/形成外科/耳鼻咽喉科/放射線科/皮膚科/精神科/麻酔科/眼科/リハビリテーション科
この記事では、専攻医についてくわしく解説しました。専攻医の期間は、医師になるうえで自身の専門を決め、その専門性を深める大切な時期です。事前に専攻医のなり方や専攻医にかかわる制度などを知っておくことで、自身の希望するキャリアに進む第一歩となります。ご自身が思い描く理想の専門医になれるよう、まずは専攻医としての自分のキャリアを考えることから始めてみましょう。
レジナビWebでは、専門医を目指す医学生・研修医の方の病院探しを応援しています。約3000件の掲載情報と、わかりやすい着目ポイントであなたの希望する病院探しをお手伝い。希望する病院がある方も、まだ希望する病院が見つからず悩んでいる方も、一度レジナビWebの病院検索を利用して今後の進路に役立ててください。
いかがでしたでしょうか?
レジナビWebでは他にも研修探しをサポートするコンテンツがたくさんあります!
もちろん、いつでも無料でご利用いただけますので、ぜひ活用してみてください。
資料請求をされる医学生の方は、うちの病院に興味を持ってくれているんだなあと印象に残りますね。